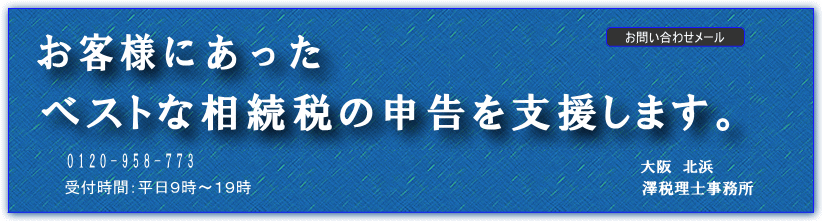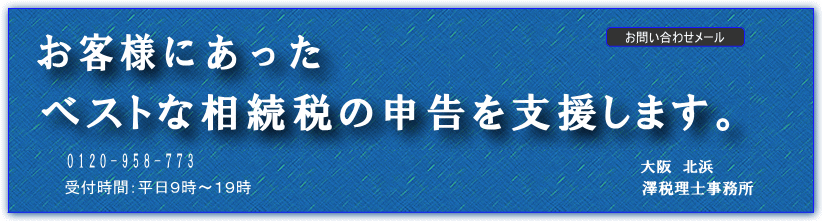> 相続税申告の基本的な流れの説明
相続税の申告納付期限を確認する
相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に
行うことになっています。
例えば、2月10日に死亡した場合にはその年の11月10日が申告期限になります。
相続財産を調べる
預貯金;預金通帳の収集
有価証券;残高証明書
土地、.建物;登記簿謄本、固定資産税評価証明書
生命保険金;各保険会社に死亡保険金を請求する
相続人を確定する
戸籍謄本、住民票などで
遺言書の存在確認する
公正証書遺言の有無の調べ方ですが 、これは公証役場に遺言者が保管されて
いるため、最寄りの公証役場に問い合わせれば遺言書の有無が判明します。
公証役場は全国の公証役場をつなぐネットワークを持っているため、どこの
公証役場に問い合わせても大丈夫です。
遺産分割協議書の作成する(遺言書で分割財産が完了している場合は不要)
相続人間で分割方法を協議する。
遺産分割協議書に基づいた相続税額の計算をする
納税資金準備をする
相続税の申告と納付を済ませる
> 基本的な流れを踏まえて、これからの相続のあり方について
相続税対策は、節税対策ではなく納税対策であり遺産分割対策です。
納税対策と遺産分割対策は同じです。
小規模宅地評価減も配偶者控除も遺産分割が整うことが前提です。
税務署を意識した納税を念頭に入れた遺産分割対策を考えます。
優遇制度を使った相続人への財産の偏りを補うだけの分割原資を確保する。
後継者の人格形成が大切です。
> 国は高齢化社会により生前に相続人等に資金が流れやすい政策を考えている
生前贈与や相続税精算課税などを活用しよう
平成72年(2060年)には、2.5人に1人が65以上、4人に1人が75以上になります。
男性84.19年、女性90.93年となり、女性の平均寿命は90年を超えます。
高齢化社会によって、父親90歳、子65歳で相続を向かえるような場合、被相続人も
相続人も高齢者になっています。この状態は、親から子へなかなか財産が移転しなく、
お金の流れがストップしますので、国全体の成長にも悪影響が出てきます。
よって、国も祖父母や親から子・孫へ資金が流れやすくなるような政策を考えています。
①教育資金の一括贈与の非課税
祖父母等から、子・孫名義の金融機関の口座に、教育資金を 一括して拠出すれば、
子・孫ごとに1,500万円を非課税とするものです。
②直系卑属への贈与税率引き下げ
平成27年から20以上の直系卑属への贈与の税率が引き下げられています。
③相続時精算課税制度の条件緩和
平成26年までは「65歳以上の親」から「20歳以上の子」へ贈与が平成27年から
「60歳以上の親・祖父母」から「20歳以上の子・孫」への贈与が対象になります。
> 資産の組み換えによる収益のアップを考えよう!
以前よく相続税対策として、駐車場にアパートを建設し、その資金を銀行から借入して
相続が発生すればその借入金を債務控除して相続税を減額する方法がよく行われて
いました。アパート建設後相続が遅くなればなるほど効果が少なくなります。この対策は
短期的な節税対策です。また、土地建物に抵当がついてますので相続が発生したら
分割しにくく、売却しずらい面もあります。
また、20年もすれば老朽化が進み補修費用が発生します。
そこで、生前に
(1)資産の棚卸をやってみましょう。
(2)優良資産の選別や不良資産を現金化しましょう。
(3)資産の組み換えを考えましょう。
固定資産の交換、事業用資産の買換え制度、等価交換制度
> 法人化による財産管理
不動産管理会社の設立効果
①個人(所得税)と法人(法人税)の税率差効果
個人にかかる所得税・個人住民税と法人にかかる法人税・法人住民税の表面税率
だけを単純に比較すると課税所得が900万円以上になると個人所得税住民税の
税率が法人税住民税等の税率より高くなります。
②所得の分散効果
法人が役員に報酬を支払うことによって、所得が法人と役員に分散されます。報酬を
受け取る個人は超過累進税率の低い税率が適用されます。
③給与所得控除によるみなし経費効果
役員報酬については、受け取った個人は給与所得として課税されますが、その際、
みなし経費である給与所得控除が適用されます。
④相続税の納税準備
大切な財産を残されたご家族へスムーズに引き継ぐためには、相続税納税資金の
準備や遺産分割のための法人化などにより資金準備を事前に行っておく必要が
あります。
ご希望のプランを選択してください。
|